
やまとわは、豊かな暮らしの提案を通して、豊かな森を育むことを目指しています。
豊かな暮らしとは、「ずっと続いていく暮らし」。人の都合だけでなく、自然の都合だけでもなく、お互いが良い関係性をつくることだと私たちは考えています。
そのためには、伊那谷にあるものと共に生きていくこと。それが大切です。
山麓農場の隣にあるパカパカ塾の馬糞を使った堆肥づくりは2020年に始まりました。
そして昨年、堆肥舎が完成。しっかりと設計された堆肥舎が完成したことで、良質な完熟堆肥がつくれる環境がようやく整いました。
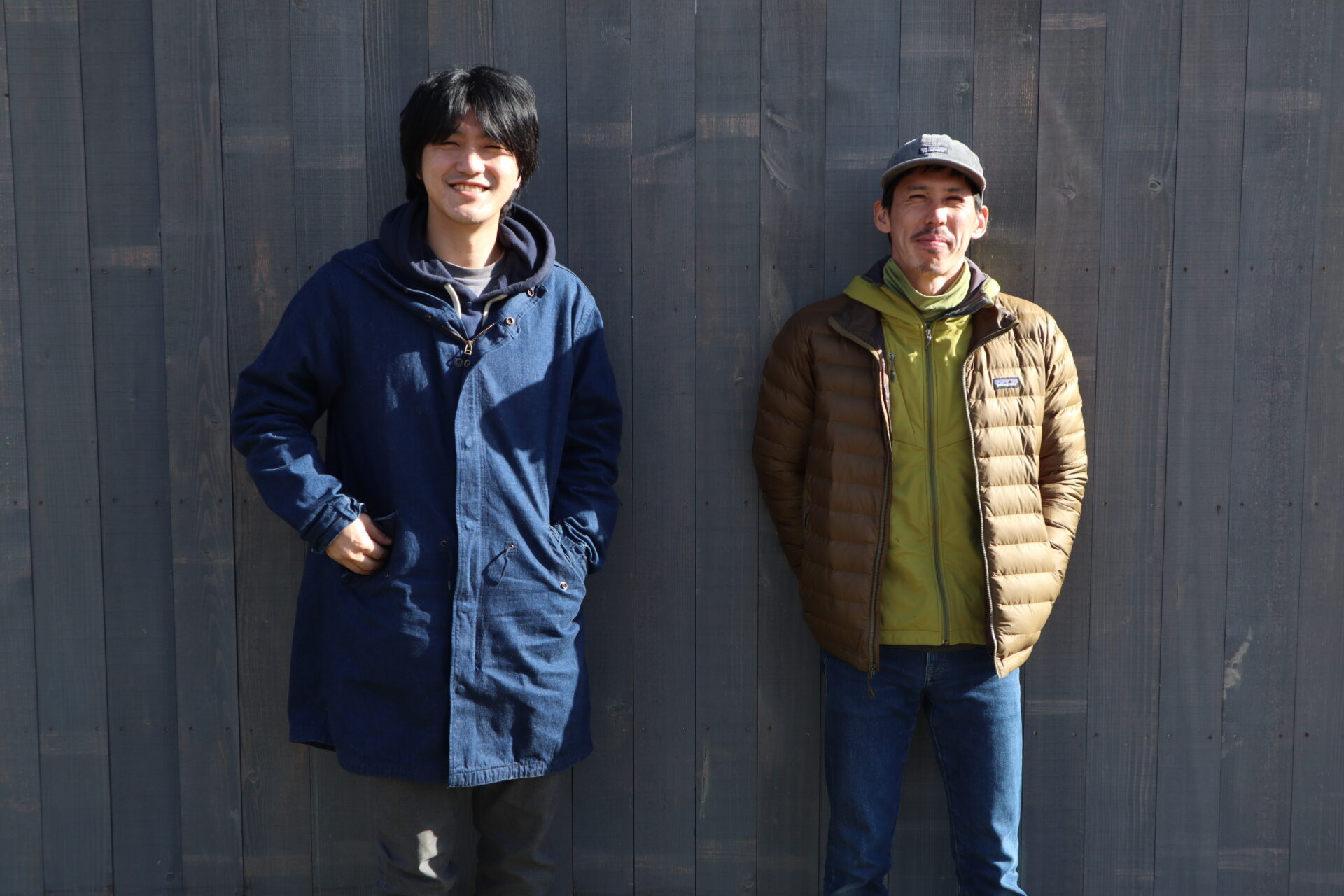
馬糞を使った堆肥づくりと1年前にできた堆肥舎について、農と森事業部の小瀧さんと奥田さんが語り合いました。
人間と微生物の共存。機械的にはできない五感を使った堆肥づくり
やまとわの堆肥は、山麓農場の隣にあるパカパカ塾のポニーの馬糞と米ぬか、もみ殻、落ち葉、赤土、鶏ふんの6種類の材料を使って作られます。
作物に直接的に働きかけて栄養になるのが肥料であるのに対し、堆肥は微生物が生きもの同士のつながりの中で間接的に作物に働きかけてくれるような効果があるといいます。
どうして農業に堆肥が必要なのでしょうか?
小瀧 : 化学肥料がない時代までさかのぼると、堆肥や有機肥料しかなかったんですよね。畜糞や鶏ふんしかなかったっていう事なんですけど、土の中にいる生きものに働きかける一番簡単な方法が堆肥だったということだと思う。
堆肥を入れることで土がふかふかになるので、環境を整えるために入れられているものという認識ですね。
奥田 : オーガニックや有機農業って言葉は面白くて、様々な生き物の有機的関係性を大事にするということが言葉の中にも入っています。有機堆肥というのも同じで、生き物の相互作用がつながり、農産物が育ちやすい環境をつくるためのものだと思います。
堆肥づくりには微生物の働きを活用をしているわけなんですけど、人と微生物の共存によって生み出される。だからこその面白さがありますが、実際は簡単じゃない。小瀧さんはその辺りやりながらどう感じていますか?
小瀧 : 難しさという点では、やっぱり目に見えないっていうところだと思います。
僕らが微生物に触れたり、存在を確認できる手段としては、温度があります。温度と微生物の活性は比例していて温度を見てなんとなく良し悪しを判断しています。
奥田 : 「温度」っていうところが生命的であり、化学的でもありますね。面白い。

小瀧 : でも、管理をする中で温度を自動的に機械で記録していればよいかというとそうではなくって。当然温度は分かるんだけど、それだけでは明らかに気づきが足りないんです。
自分で現場に行って堆肥に温度計を刺して測った温度が機械で測った時と同じ50度でも、堆肥の状態を目で見たり手で触ったり、においをかいでみたり。機械で温度を測るだけでは得られない温度以外の情報の蓄積も大事だなと感じています。
奥田 : データも大事だけど、自分の五感も育むような感じですね。身体性が求められますね。

小瀧 : ただ単に有機物が分解されて無害化されれば良いという話だったらそこまでしなくて良いのかもしれないんですけど、品質の高い堆肥を作りたいという目的があるという意味では人の手入れがやっぱり重要だと感じています。
奥田 : 微生物は生きものであって道具ではない。生きものとして接するということなんでしょうね。
小瀧 : そう思いますね。ともすれば、作業になってしまうじゃないですか。僕自身、陥りやすいなと感じています。
奥田 : 効率的にやろうと考えてしまう?
小瀧 : 効率性もそうだけど、切り返しをする時ローダーに乗ってガサガサッと作業をするとします。それって作業自体は進んでいるかもしれないけど、その堆肥の状態を感度高く感じ取れるかとかそういうことが、生命を意識的に考えるという面で重要だと思っています。
奥田 : どれだけ注意深く見るかみたいな話になって来るんですよね。
小瀧 : 温度だけでなく堆肥をにぎった時の触感、においとか。においも発酵過程で変わって来るし、白っぽく見える菌がだんだんと見えなくなってくるとか。
五感を使うということは言葉で言うのは簡単だけど、本当に難しくて…日々気づく力や観察力を試されているようにも感じます。その中でも土が持つ力にワクワクしたり、目に見えない世界を想像することが面白いですね。

“廃棄のデザイン”と“100を0にする堆肥づくり”
目に見えない微生物の社会性や営みに、人間の手が加わってできあがる堆肥。小瀧さんは、堆肥づくりをする中で、どんなことを感じているのでしょうか?
小瀧 : 僕は「使えないものを使えるものにしている」というところに日々感動しています。めっちゃ良いことをやっているなっていう感じがする。
昔、奥田さんみたいなクリエイティブの仕事をしている人に憧れを持っていた時があって。0から1を生み出す人ってかっこいいなと思っていたけど、今やっている仕事は100を0にする仕事だなと思っていて。
奥田 : 100を0?
小瀧 : 使われなくなったというか、いわゆるゴミをもう一度使える状態の0に戻すというイメージ。0に向かって行く営みにやりがいを感じるし、とても面白いと思っています。
この面白さが伝わる人がどのくらいいるか分からないですけど…自分自身の興味は、そういうところで沸き立つものがあります。

奥田 : 面白いですね。やまとわは循環を大事にしているから、そこの終わりを考えるとか、終わりから次の始まりに繋げるというのは重要な視点ですよね。pioneer plantsでは「捨てやすさのデザイン」っていうのを考えてやっていますけど、“終わりから始まる”っていうことを僕らは身につけないといけないと思うんですよ。
小瀧 : 終わりから始まる?
奥田 : 何かをつくる前に「どうやってこれを処分するのかな?」というところから考える。そのことが産業の中に習慣化されないと、使い終わった後に埋め立てを続けないといけなくなってしまう。人間は何かを作る時、“廃棄のデザイン”をして来なかった。

奥田 : 未利用資源を集めて堆肥を作る。でも、農業ってそういうものを活かすための産業ではないという話もあるんですよね。農業の中には、よりおいしいものをつくるとか量を沢山つくるっていう技術がいっぱい詰まっていますし。
そう考える時、良い野菜を作るための堆肥づくりと未利用資源を活用した堆肥づくりは、まるで相反するもののように存在するんですけど、これをひとつにまとめ上げるのが人間の技術力。うまくていい野菜ができるし、暮らしの中で出て来る未利用資源はまた土に還るというような、そういう全体のデザインをし直すにはどうしたら良いかっていうことなんですよね。
小瀧 : 堆肥づくりの技術と、やまとわっていう会社が何をしているのかというストーリーと規模感、その2点から、堆肥事業をデザインしたいというところが面白い。
社内の事業で出る未利用資源の処理を外部に任せるのではなく、堆肥の技術を使うことで社内で使えるものに変えていく。ひとつの会社の機能として、そこまで持っているところって少ないんじゃないかな。
奥田 : 地域全体でそういう仕組みを実現できたら最高に楽しいけれど、まずは僕らみたいな小さな会社が本気を見せる。
例えばいきなり大きな建物ができて、そこで地域の人達がコンセプトを知る間もなく、たくさんの牛糞が土になっていく。そういうことよりも、小さくて暮らしに近いところから起こっていくということの方が大事さみたいなものがあるかなと思うんです。
小さなところで実現するオルタナティブをデザインするっていうのが、やまとわの堆肥舎の役割なんですよね。

自然の営みと人の営みが関わり合って循環していく暮らし。
堆肥舎は未利用資材を使って堆肥を作る場所としての役割だけでなく、やまとわのシンボル的な存在でもあります。
全体が巡って違和感のない状態の中に、農業や他の産業もあり、私たちの暮らしそのものがあるということ。それが「ずっと続いていく暮らし」につながると私たちは考えています。
寒さ厳しい冬が終わると間もなくやって来る春。山麓農場での農作業は、堆肥を畑に入れることからスタートします。

